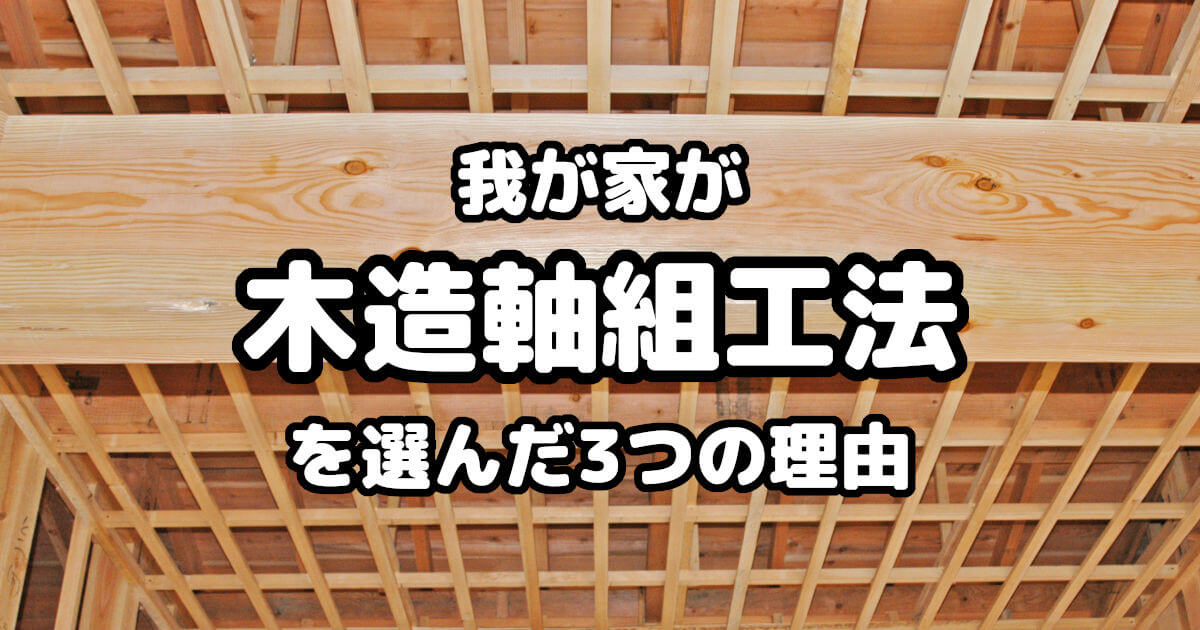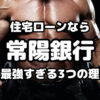こんにちは、小野です
我が家では土地購入からの注文住宅を考えています。
そのため先日、土地の売買契約と、住宅会社への申し込みをしました。
今回ぼくらが申し込んだ住宅会社「ツリーハウジング」は木造軸組工法で家を建てる会社です。
今日は小野家が家を建てるにあたって「なぜ木造軸組工法を選んだのか」について書きたいと思います。
数ある中から、我が家は木造軸組工法を選んだ


そもそも、家を建てる工法(構法)には様々な種類があります
- 木造(軸組 / 壁式 / SE)
- 軽量鉄骨造(軸組 / プレハブ)
- 重量鉄骨造(軸組 / ラーメン)
- 鉄筋コンクリート造(壁式 / ラーメン)
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(壁式 / ラーメン)
上記以外にもたくさんあります。各ハウスメーカーが独自開発した工法も含めれば、もう数え切れないほどです。
そんな中から、ぼくらは「木造軸組工法」で家を建てると決めました。
住宅会社を選ぶ際にも、木造軸組工法で建てられることを条件の1つに設定したほどです。
我が家が工法選びで意識した5つのポイント


最終的にぼくらは木造軸組工法を選んだわけですが、その際に意識したポイントをご紹介します
大切な、一生住むかもしれないマイホームを建てる工法ですからね。
適当に選ぶわけにはいきません。
そこで意識したのが以下の5つです。
工法選びのポイント
- コストの安さ
- 住宅会社の数
- 断熱性能の高さ
- 間取りの柔軟性
- 解体のしやすさ
ちなみに、わたしはデザインや住心地重視で、こういった細かいことにはあまり興味がありません


というわけで、細かいことはぼくの担当です
工法選びのポイント① コストの安さ
まずはなんと言ってもコストが安いことが重要です。
ぼくらは首都圏で土地を購入するので、建物部分に大きな予算を割くことができません。
年収もそれほど高いわけじゃありませんし、そもそも貯金も50万円しか無いし・・・。
家を建てるにあたってのコストの安さは重要なポイントです。
工法選びのポイント② 住宅会社の数
例えば「ビッグフレーム構法」で家を建てたい場合、住宅会社は住友林業に決定です。
このように、特殊な工法を選ぶほど、建てられる会社が限られてきます。
住宅会社選びの選択肢はなるべく多いほうがいいので、対応できる会社が多い工法を選びたいと思いました。
工法選びのポイント③ 断熱性能の高さ
高気密・高断熱の家って流行ってますよね。
ぼくもご多分にもれず、高気密・高断熱な家を建てたいと思っています(「超高性能」まではいりませんが・・・)。
家の断熱性能は工法によっても変わってきます。
したがって(なるべく安価に)気密・断熱を取りやすい工法を選びたいと考えました。
工法選びのポイント④ 間取りの柔軟性
小野家は今、ぼく・みたらし・しらたまの3人家族です。
あと1人、子供が欲しいと思っています。
・・・もしかしたら、次の子は双子かもしれませんよね。
・・・もしかしたら、ぼくやみたらしの親と同居になるかもしれませんよね。
・・・もしかしたら、病気や事故、廊下などで1階でしか生活できなくなるかもしれませんよね。
そういった、家族構成やライフスタイルの変化に応じて、柔軟に間取りを変更できる工法を選びたいと思いました。
また将来的に家を売却する際にも「間取りの柔軟性(=リノベーションのしやすさ)」は高評価になるはずで、高価格での売却につながると考えています。
工法選びのポイント⑤ 解体のしやすさ
将来的に家の建て替えや売却をする際、ネックになるのが家の解体です。
ぼくらが購入したワク土地Eには現在、軽量鉄骨造の古屋があるんですが・・・
実際にこの解体費がネックとなり、買い手が付きづらかったと聞きました。
- ぼくが家を売りたくなる
- しらたまが家を建て替えたくなる
いつの日か、こんな瞬間が高確率でやってきますよね。
なるべく解体しやすい工法で家を建てておいたほうが、将来的に良いと考えました。
木造軸組み工法を選んだ3つの理由


冒頭でお伝えした通り、上述のポイントを踏まえ・・・
ぼくらは最終的に、木造軸組工法を選択しました。
その理由が以下の3つです。
木造軸組工法を選んだ理由
- 常に低コスト
- 断熱性能が高い
- 何事にも柔軟に対応
木造軸組工法を選んだ理由① 常に低コスト
木造軸組工法は「在来工法」とも呼ばれ、日本で古くから採用されてきました。おそらく日本で一番使われている工法です。
そのため対応できる工務店が多く、その中には非常に安価に家を建てられる会社もあります。
そして鉄骨造や鉄筋コンクリート造などと違い、建物自体が軽くなるので、地盤改良もそれほど強固にする必要がありません。

つまり初期コストが安い!!
家を建てたあとのメンテナンスも、対応できる会社が多いので選択肢に困りません。
中には激安でやってくれる会社もあることでしょう。

つまりランニングコストが安い!!
家を壊す場合も、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と違って重機でかんたんに破壊できます。
廃材の処分費用も安価です。

つまり解体コストが安い!!
というわけで、木造軸組工法は入口から出口まで、常にコストを抑えられるんです。
これは大きな魅力でした。
木造軸組工法を選んだ理由② 断熱性能が高い
鉄骨造は木造に比べて断熱性能をあげにくいという特性があります。
また鉄筋コンクリート造は断熱性能は高いですが、建築費や地盤改良費が高額になりがちです。
なるべく低コストで高性能な家を手に入れたいと思っているぼくらにとって、木造はかなり魅力的に感じました。
木造軸組工法を選んだ理由③ 何事にも柔軟に対応
2x4などに代表される木造壁式工法(枠組壁工法)にくらべ、木造軸組工法は柔軟性が高く、間取りの制限が少ないという利点があります。
将来的に間取りを変更しやすいため、家族構成やライフスタイルの変化に柔軟に対応できます。
また売却を考えた場合でも、自由に間取りを変更できる構造の家のほうが、売れやすいと考えました。
さらに上述した通り、木造軸組工法は日本で最も採用されている工法です。
つまりどこの会社でもリフォーム・リノベーションできます。
例えばハウスメーカー独自の工法で建てられた家の場合・・・その会社でしかリフォームできないなんてことも少なくありません。
数十年後にその会社が生き残っている保証はありません。仮に生き残ってたとしても、その工法を採用し続けているかどうかわかりませんよね。
一方で、木造軸組工法がたかだか数十年で使われなくなるなんてことはありえません。
もしも家を建てた会社がなくなっても、木造軸組み工法ならどの会社でも柔軟に対応ができるでしょう。
木造軸組工法のデメリットと小野家の考え


ここまで木造軸組工法の良いところばかり伝えましたが、もちろんデメリットもあります
どの工法も一長一短ありますから。
ここでは、木造軸組工法のデメリットとしてよく指摘される部分の紹介と、それぞれのデメリットに対しぼくらがどう考えたのかについて紹介します。
木造軸組工法のデメリット
- 蟻害
- 災害への弱さ
- 構造的な限界
- 長い工期と品質のばらつき
木造軸組工法のデメリット① 主要構造部含め、蟻害に弱い
「蟻害」はつまり「シロアリの被害」のこと。
木造は主要な構造部分を含めほぼ全てを木でつくりますから、当然のごとくシロアリに弱いです。
シロアリに主要構造部を食い散らかされると、大規模リフォームや建て替えが必要になってしまうこともあります。

かなりデカいデメリットですね
小野家の考え:他の構造にも蟻害はある。対策すれば多分大丈夫でしょ
鉄骨造や鉄筋コンクリート造などでも木を使います。
つまり程度の差はありますが、どんな構造でも蟻害は起こりえます。
どんな構造であれ蟻害対策は必要ですから「だったら木造でもいいんじゃ?」と考えました。
しっかりした対策さえすれば大丈夫だろうと楽観的に考えた形ですね。
そのかわり・・・
- ホウ酸による防蟻処理
- 断熱材にセルロースファイバー
などなど、蟻害を防ぐための仕様を積極的に選び対策しています。
木造軸組工法のデメリット③ 災害に弱く修繕も難しい
木造は木でつくられるので火災に弱いです。
また水に沈むと極端に強度が弱まるので、水災にも弱い。
そして(鉄筋コンクリート造などと比べると)強度的に震災にも強くはありません。
こんな感じで、他と比べて木造は災害に弱いと言えるでしょう。
また木造の家が被災すると、修繕が難しくなるほどのダメージを受けてしまうことも少なくありません。
小野家の考え:対策すればなんとかなる!
最近は火に強い優秀な建材がたくさん売られています。
それらを積極的に使うことで、少しは火に強い建物にできると思います(一応火災保険もありますしね)。
水災については土地選びで被災の確率を大幅に下げられます。
震災だけは逃れようがありませんが・・・
許容応力度計算による構造計算で耐震等級3を取得すれば、ある程度の品質を担保することができるでしょう。
というわけで、災害への弱さはそれなりの対処法が確立されていると考えました。
木造軸組工法のデメリット④ 構造的な限界で間取りに制約がある
木造軸組工法は鉄筋コンクリート造などに比べると「できないこと」が多いです。
例えば
- (極端に)大きな開口
- 大きな吹き抜け
- 柱のない大空間
このような開放的なつくりにするには、木族軸組工法では限界があります。
ところどころに耐力壁が必要だったり、抜けない柱が出てきたりと・・・構造的な制限が色々あるんです。
小野家の考え:他の構造にもあるし、許容できる!
構造的な限界による間取りへの制限は、木造軸組工法以外の工法にも存在します。
むしろ、木造軸組工法は比較的少ないほうなはず。
開放的な間取りはたしかに苦手ですが、それは設計や見せ方次第でどうにかなるでしょう。
というわけで、木造軸組工法の制限によるデメリットはぼくらは許容できると考えました。
木造軸組工法のデメリット② 工期が長く、品質にバラつきが出やすい
例えば壁式工法やプレハブ工法の場合、工場にある機械で家の部品をつくります。
現場の大工さんたちは運ばれてきた部品を組み立てるだけでOKです。
つまりは大量生産品ですので、品質のバラつきが少ないんです。
しかも現場では組み立てるだけなので、工期が短くてすみます。
対して木造軸組工法は職人さんの技術に頼る部分が大きいので、どの大工さんに頼むかによって完成度が大きく変わります。
人力が必要なので、工期も長くなりがちです。
小野家の考え:工期は問題なし。品質は会社選びで担保。
幸いなことに、ぼくらはあまり急いでません。引っ越しまで、1年以上の猶予があります。
したがって工期の長さは問題になりません。
品質が低いのは嫌ですが・・・これは住宅会社選びで気をつけるだけで、ある程度防げると思いました。
お金があったらSE構法を採用したかった


というわけで、メリット・デメリットを踏まえた上で、我が家は木造軸組工法を選んだんです
ですが本音を言えば、木造軸組工法よりも本当はSE構法を採用したかったんです。笑
「重量木骨造」や「木骨ラーメン構造」などと呼ばれる工法でして、木造の一種ですね。
SE工法なら、木造軸組工法ではできない
- 大きな開口部
- 巨大な吹き抜け
- 大きな張り出し
- 柱のない大空間
なんかを実現できるそうで、木造軸組構法の弱点をかなり克服しているんだとか。地震にも強いそうです。
対応できる住宅会社が少ないというデメリットはありますが、かなり魅力的に感じておりました。
ですが・・・

SE構法の家は高い
ぼくら、50万円しか貯金ないですから。
土地も持ってないので、建物にそこまでのお金を投下することができず、断念したんです。
お金さえあれば、SE構法で家を建てたかったなぁ・・・。
もし次に家を建てる機会があれば(そしてお金があったら)、SE構法を選ぶと思います
まとめ:なんだかんだで、木造軸組工法がNo.1だと思う
木造軸組工法を選んだ理由
- 常に低コスト
- 断熱性能が高い
- 何事にも柔軟に対応

上記の理由から、ぼくらは木造軸組工法を選びました
もちろんデメリットもありますが、きちんと対策すれば全て許容できると思ったんです。
解説した通り、木造軸組工法は日本で古くから採用され、最も多くの家で使われている工法です。
多くの家で採用されるには、それなりの理由があるということで・・・
なんだかんだ、木造軸組工法が最もバランスが良く、最強なんじゃないかなと思いました。
まぁ、もし資金的に余裕があるのなら、ぜひSE構法をオススメしたいですけどね。笑