
今回の記事はこういう危険思想を持った方のための記事。答えは

って感じなので、これで満足な方は読まなくてOK。
ぼくの本業はマーケター。
SEOを始めとするWebマーケティングを中心に、マーケティング施策全般を企画・実行することでご飯を食べています。
ぼくみたいにSEOをしっかり学んだ人なら「SEOの歴史」を誰でも知ってます。
そして歴史から学べるのがこれらSEOの基礎。
SEOの基礎
- スパム行為は無意味
- 検索意図の理解が必須
- 高いコンテンツ品質が大前提
- 検索体験の向上がこれからのカギ
今回はSEOの歴史を解説します。
そこから得られる4つの基礎をぜひ覚えていってください。
4行でわかるSEOの歴史
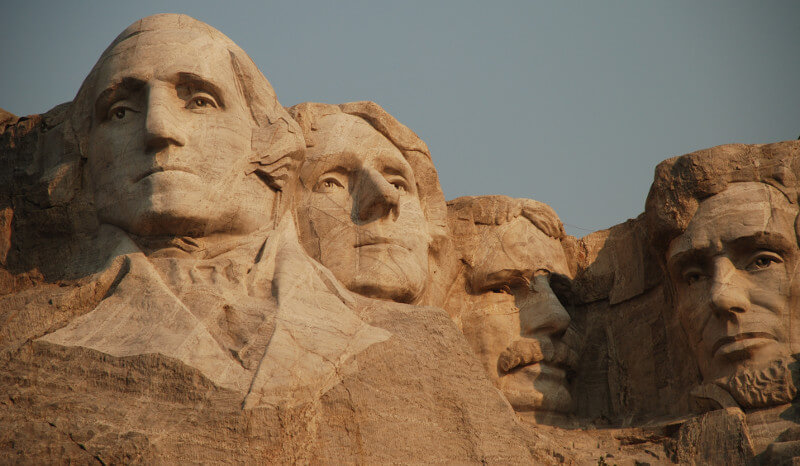
昔、偉い人がこんなことを言いました。

SEOの歴史を学べば
- NGなSEOがわかる
- 現在の重要ポイントがわかる
- これからのSEOに予測がつく
こういった効果を得られます。SEO対策の効率が格段に良くなるんでオススメです。
そして、SEOの歴史を簡潔にまとめるとこうなります。
SEOの歴史まとめ
- 検索エンジン誕生
- スパム行為の隆盛
- 技術革新によるスパム撲滅
- 検索意図とコンテンツの理解力向上
この歴史の中で具体的にどういうことがあったのか、詳細に解説していきます。
1990年代のSEO:検索エンジン爆誕

- Googleの誕生前
- ディレクトリ型が主体
- 後半にロボット型が登場
Googleはまだ登場しませんが、1990年代に「検索エンジン」がこの世に初登場します。
当時は「ディレクトリ型」と呼ばれる形式が主体。
細かい説明はしませんが、検索エンジンへの掲載に登録と審査が必要だったため、一般のWebサイトは掲載されていないのが当たり前でした。
1990年代後半に現在主流となっている「ロボット型」の検索エンジンが登場します。
2000年代のSEO:スパム行為の隆盛

- Google登場
- 被リンク数が重要に
- スパム行為が大流行
2000年代に入り、ついにGoogleが登場。
被リンク数を重要視する現在の検索アルゴリズムの基礎が開発されました。
SEOのNG行為「スパム」の誕生
検索エンジンは、検索結果に良質なコンテンツを表示することで稼ぎたいと考えています。
こちらの記事で解説した通りです。
一方で、スパマーは「楽に大量のアクセスを集めて稼ぎたい」と考えているため、検索エンジンをごまかすためのスパム行為が考え出されました。
スパム行為が大流行
この記事で紹介したようなスパム行為が超流行ります。
≫ 知らないとまずいSEOのNG行為!過去に流行ったスパム行為まとめ
スパムはかなり効果的、というよりスパムをやらないと上位表示できないというカオスな状況だったので、かなり多くの企業がスパム行為に手を染めました。

2010年代前半のSEO:スパム撲滅

- Googleのシェア拡大
- スパム行為が殲滅される
- 検索意図の理解が始まる
このころまでには検索エンジンの淘汰が進み、Googleが圧倒的なシェアを持つようになりました。
そしてGoogleの技術力が一気に高まったこともあり、スパム行為の殲滅が始まります。
歴史を変えた2つのアップデート
今でも語り継がれる歴史的なコアアルゴリズムのアップデートがGoogleで実施されました。
伝説のアップデート
- ペンギンアップデート
- パンダアップデート

これでスパマーのほとんどが駆逐されました。
ペンギンアップデート(2012年4月)
隠しテキストやクローキングなど、各種スパム行為を撲滅するためのスパマー殺戮アルゴリズムです。
ユーザーに良質なコンテンツを提供していても、過去のスパム行為を見つけて順位を叩き落とすケースがありました。

パンダアップデート(2012年7月)
問答無用で低品質コンテンツの順位を叩き落す恐怖のアップデート。
逆に高品質コンテンツは順位が上がりました。
まじめなサイトにとっては最高のアルゴリズムと言えます。

現在はコアアルゴリズムに統合
これら2つのアップデートは当時、Googleが手動で行っていました。
しかし2020年現在、コアアルゴリズムに統合されて常に発動状態です。

検索意図の理解が始まる
「ハミングバード」という2013年9月に実施されたアップデートにより、ユーザーの検索意図の理解が始まります。

こういう「検索意図」が何なのかいまいちわかっていない方のために簡単に具体例で解説します。
具体例:「東京駅 駐車場」の検索意図
ハミングバード以前は【東京駅 駐車場】と検索した場合
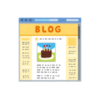
みたいな文章を掲載したコンテンツがランキング上位に表示される、なんてことも多々ありました。


現在の検索結果の特徴
- 東京駅近郊の駐車場がリスト化
- 対象の駐車場を地図表示
【東京駅 駐車場】という検索キーワードの裏にある

というユーザーの意図を理解して、検索結果に反映しています。

2010年代後半のSEO:コンテンツ品質とユーザー体験の重要視

- 検索意図とコンテンツ内容の理解が進む
- 高品質コンテンツしか上位表示されない
- YMYLにおけるEATの重要度が上がる
- 検索体験の向上が重要になる
2010年代後半にはスパム行為はほぼ無効化されました。
代わりにコンテンツ品質と検索意図理解の流れがより一層強化されます。

キュレーションメディアの栄枯盛衰
2010年代中ごろに、他サイトの情報をまとめて記事化する「キュレーションメディア」が非常に流行しました。
検索上位にたびたび表示され、DeNA社をはじめとするキュレーションメディア運営企業は大きな成功を手にします。
WELQ問題の勃発
しかし、2016年秋に起きた「WELQ問題」で状況は一変。
当時DeNA社が運用していた「WELQ」というヘルスケア系のキュレーションメディアが発端となって起きた一連の騒動です。
これをきっかけに、YMYL領域におけるEATの重要性がさらに高まりました。
≫ 日本だけで生じたYMYLの転換点「WELQ問題」を解説する
日本語検索アップデート(2017年2月)
WELQ問題をきっかけに日本語検索のみで実施されたアップデートです。実質的な「キュレーションメディア虐殺アルゴリズム」。
思想としては2010年代前半に行われたパンダアップデートと同じです。
コンテンツの品質が高いサイトは上位表示され、低いサイトは叩き落とされました。
コンテンツと検索意図の理解力がパワーアップ
AIの導入が進んだことで、コンテンツの内容や品質、検索意図の理解力が異常に高まります。
具体的にはこれら3つの言語処理アルゴリズムが追加されました。
AIを使った新たな言語処理
- RankBrain (2015年10月)
- ニューラルマッチング (2018年9月)
- BERT (2019年10月)
要は


こういうことです。
検索体験の向上
検索意図の理解以外にも、ユーザーの検索体験を改善しようという動きが活発になりました。
モバイルファーストインデックス(2018年3月~)
検索順位を決める基準をPCサイトからスマホサイトに変更しました。
スマホサイトとPCサイトとで表示しているコンテンツが異なるサイトなんかは、検索順位が下がるなどの影響が出るようになりました。

スピードアップデート(2018年7月)
極端にページの表示速度が遅いサイトの検索順位を落とすというアルゴリズムです。
早ければ早いほど上位表示される!ってわけじゃないので注意しましょう。

良いコンテンツならページが遅くても上位表示されます。
2020年代、これからのSEO

- EAT
- 検索意図
- 内部対策
- コンテンツ品質
これらがより重要性を高めていくことは間違いありません。
詳しくはこちらの記事で解説したのでぜひご確認ください。
≫ 2020年代、これからのSEOで重要になる4つのポイント
まとめ:SEOの歴史を今後の運用に活かそう
SEOの歴史についてまとめました。
思ってたより濃い記事になりましたね・・・。
この一連の流れから学べるSEOの基礎がこれ。
SEOの基礎
- スパム行為は無意味
- 検索意図の理解が必須
- 高いコンテンツ品質が大前提
- 検索体験の向上がこれからのカギ
これまで紆余曲折あったものの、最初から一切変わっていないのが「コンテンツ品質が超重要」ってことですね。
これに加えて、検索意図の理解や検索体験の向上が歴史の流れとともに加わってきています。
ぜひこれらの学びを胸に、ブログ運用やSEO対策に取り組んでいってください。
